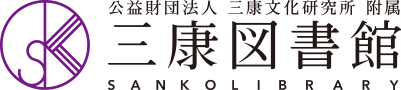2025年度開催報告
第1回公開講座(ハイブリッド開催)
開催日時:2025年5月12日(月)16:00~18:00
開催方法:ハイブリッド開催(Zoomミーティング・会場 閲覧室)
講座:
①石川琢道(三康文化研究所研究員・大正大学教授)
「増上寺四六世 妙誉定月上人について」
②柴田泰山(三康文化研究所研究所研究員・浄土宗総合研究所研究員)
定員:事前申込制 先着順 オンライン80名 会場20名
参加費:無料
内容: この度、三康文化研究所において石川琢道研究員(専門分野:中国浄土教思想史)と柴田泰山研究員(専門分野:中国仏教・浄土宗学)による2025年度第1回公開講座を5月12日に会場とオンライン(ZOOM)を併用してのハイブリット形式で開催しました。
石川琢道研究員「増上寺四六世 妙誉定月上人について」
妙誉定月上人(1687~1771)は、江戸時代中期から後期に増上寺および諸檀林の住持を務め、『天台戒体明灯章』『獅子絃』など多くの著作を残した名僧です。伊勢の西光寺で得度後、増上寺南谷で学び、維摩経や倶舎、唯識の講義を重ねるとともに、経蔵の蔵書補充に尽力しました。九代将軍家重公の葬儀では大導師を務め、山下谷に妙定院を建立して将軍位牌を奉安。その後隠棲し称名念仏の中で示寂されました。本講座では、定月上人の足跡と思想的影響を紹介しました。あわせて『妙誉大僧正略伝』の校訂成果や写本の資料的意義についても触れ、定月上人研究の今後の展望を探りました。
柴田泰山研究員「浄土宗名越派の教学研究序説」
室町時代から江戸時代にかけて、浄土宗には現在の白旗派とともに、名越派という一派が北関東から東北地方にかえて隆盛していました。しかしこの名越派は明治時代に白旗派に統合されることとなり、現在では積極的な研究対象になっているとは言い難い状況です。そこで今回は初期名越派に着目し、名越派伝書を伝える月形函の書目や、『先師良山口筆』などを通じて、初期名越派の教学をどのように研究していけばいいか考察を試みました。
今回も、寺院関係者の方、研究者の方、浄土宗関係者の方、他宗派関係者の方、仏教にご興味をお持ちの方等59名(内会場参加者8名)の方から聴講のお申し込みをいただきました。また、マスコミ関係者として、株式会社中外日報社の記者の方が取材されました。ご聴講された皆様に心からお礼申し上げます。
聴講された方々のお声の一部をご紹介します。
「定月上人、名越派、いずれも初めて知り、関心を持ちました」
「名越派に興味を持ちました」
「楽しかった」
第2回公開講座(ハイブリッド開催)
開催日時:2025年10月6日(月)16:00~18:00
開催方法:ハイブリッド開催(Zoomミーティング・会場 閲覧室)
講座:
①林田康順(三康文化研究所研究員・大正大学教授)
「法然上人における平和思想-ご生涯とご法語に学ぶ-」
②宇髙良哲(三康文化研究所研究指導員)
「南光坊天海の自筆書状について」
定員:事前申込制 先着順 オンライン80名 会場20名
参加費:無料
内容: この度、三康文化研究所において林田康順研究員(専門分野:法然浄土教・浄土宗学・日本浄土教)と宇髙良哲研究指導員(専門分野:中日本近世仏教史・浄土宗・天台宗・真言宗・修験宗)による2025年度第2回公開講座を10月6日に会場とオンライン(ZOOM)を併用してのハイブリット形式で開催しました。
林田康順研究員「法然上人における平和思想-ご生涯とご法語に学ぶ-」
令和七(二〇二五)年は、終戦から八〇年を迎えます。この大戦におけるわが国の犠牲者は三一〇万人余、全世界では八五〇〇万人余と言われます。日本の、いや世界の歴史上、もっとも悲惨な出来事であったと言えるでしょう。浄土宗平和協会では、戦争中の浄土宗の動向を検証した『浄土宗「戦時資料」に関する報告書』(令和五年三月三一日)を刊行しました。本講座は、法然上人のご生涯とご法語に学びながら、法然上人における平和思想についてご一緒に考えていきたいと思います。
宇髙良哲研究員「南光坊天海の自筆書状について」
私はかつて『南光坊天海発給文書集』を刊行して、その後の原帖をあわせて約400点余の天海の発給文書を写真版入りで紹介をした。今回の発表ではその中で天海の自筆書状を特定して紹介したい。右筆の作成したものや公文書などと区別して整理して発表したい。
今回も、寺院関係者の方、研究者の方、浄土宗関係者の方、他宗派関係者の方、仏教にご興味をお持ちの方等43名(内会場参加者7名)の方から聴講のお申し込みをいただきました。ご聴講された皆様に心からお礼申し上げます。
聴講された方々のお声の一部をご紹介します。
「三康図書館所蔵の古文書等資料について解説いただけるのはうれしい。古文書が読めるようになると楽しいと思うが、なかなか勉強する時間がなく難しいので解説いただけると古文書に親しみが持てる」
「仏教も歴史も未明なものです。御高名な先生方の講義を、拝聴させていただき、幸甚です。資料も詳しく、Kindleにも保存でき、繰り返し、見ることでき、有り難く存じます」
「歴史を調べる上で、正しい資料に基づいて、研究すること、大事であるとわかりました。また、資料の正しさを判断するには、深い経験が必要と思いました」
なお、今後の公開講座ですが、未定となっております。詳細がわかり次第、HP等でご連絡いたします。